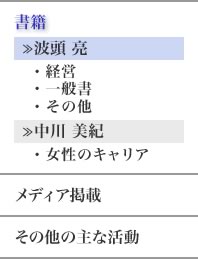●詳細
|
 |
 |
 |
■ 戦略策定概論
―企業戦略立案の理論と実際
波頭亮(著)
産能大学出版部
価格:2,310円(税込)
→Amazon.co.jp
今日、企業経営を行う上で「戦略」の重要度はますます度合いを高めている。しかし、いざきちんと「戦略」について学ぼうとすると、それはなかなかやっかいなチャレンジであることに気付く。その理由は大体次の三つに集約される。一つは「戦略」と呼ばれるものが極めて多岐にわたるものである為、どうアプローチしてよいのか途方にくれてしまうと言う点、二つ目はそもそも戦略がどのようなものか明確でない為、何を学べば戦略を策定できるようになるのかが分からないという点、そして三つ目は戦略のベイシックについて書かれ、コンサイスにまとまっている本が存在しないという点である。本書は、これらの問題点を意識しながら、「戦略」と「戦略策定ノウハウ」についてまとめたものである。ポーター、コトラー、アンゾフの戦略理論からSISまでを体系的に網羅するとともに、ミノルタのα-7000、オロナミンC、カシオ、ポルシェ、モランボンのジャン、ヤマト運輸、ソニーのウォークマン等、実際に成功した戦略、失敗した戦略等の事例を豊富に取り入れ、理論から実際の事例まで幅広く扱っている。また古典的な戦略論から現在最も注目されている戦略分野までを視野にいれた、ビジネスマンなら誰もが興味深く理解できるように工夫された完全なる「戦略」のテキストである。
本書の目次
第Ⅰ章 戦略とは
I-1 戦略の定義
I-2 戦略策定という行為
I-3 戦略的思考
I-4 企業戦略の構造
第Ⅱ章 企業戦略の類型
II-1 戦略ドメイン策定の類型
II-2 事業戦略の類型
II-3 プロダクト・ライフサイクル
第Ⅲ章 PMSの策定プロセス
III-1 PMSとは
III-2 PMSのプロセス
第Ⅳ章 マーケティング戦略
IV-1 マーケティングとは
IV-2 マーケティングの4P
IV-3 事例紹介
第Ⅴ章 機能別戦略
V-1 機能別戦略とは
V-2 生産戦略
V-3 技術戦略
V-4 営業戦略
V-5 物流戦略
V-6 戦略的情報システム |
 >>前のページに戻る >>前のページに戻る |
|
 |
 |
|
■ 組織設計概論
―戦略的組織制度の理論と実際
波頭亮(著)
産能大学出版部
価格:2,730円(税込)
→Amazon.co.jp
今日、世界的なレベルで規制緩和が進展し、また急速なIT時代の発達に伴って、企業はかつてないほどの熾烈な競争状況に突入している。こうしたメガコンペティションの時代を迎えた今、企業では経営のあり方そのものを抜本的に見直す動きが急である。また、今日の企業の重要な経営課題は、「戦略と組織の融合」と言われるように戦略テーマと組織テーマが表裏一体で繋がっており、組織論がかつてないほどに重要性を増してきている。また、ITの発達に起因する組織運営の方法論の様変わりも組織論への注目度を高めている。この流れに的確に対応する為には、組織というものをきちんと理解することが必須であることは言うまでも無い。本書はこうした問題意識を念頭に、「組織」「組織設計」「現代の戦略的組織制度」についてまとめたものである。フラット型組織、カンパニー制のあり方からERP、EVAの活用法まで、企業の戦略的アクションを実現するための、組織制度の設計・導入の勘所を明快に解説している。企業組織のあるべき姿を体系的・具体的に理解し、戦略的組織制度を構築するための概論として構成し、理論的でありながら具体的、高度な内容を扱いながらも解りやすい「組織」のテキストとなっている。
本書の目次
第Ⅰ章 組織とは
I-1 組織とは
I-2 組織設計の考え方
第Ⅱ章 組織設計のプロセス
II-1 プロセスの基本設計
II-1 個別ステップの展開
第Ⅲ章 現在の戦略的組織制度
III-1 組織の時代
III-2 現代の組織戦略
III-3 現代の戦略的制度 |
 >>前のページに戻る >>前のページに戻る |
|
 |
 |
|
■ 思考・論理・分析
―「正しく考え、正しく分かること」の 理論と実践
波頭亮(著)
産能大学出版部
価格:2,310円(税込)
→Amazon.co.jp
今日、「論理的思考」はますます学校教育やビジネスにおける様々な局面でその重要性を増し、まさに時代の要請である。しかし、これまでの教育で“大量の知識を覚えてその中から答えを探す”という方法論しか身につけてこなかった日本人にとって、“自分で論理的に考え独自の答えを創り出す”のは到底容易ではなく、今尚多くの人がその有効な学び方さえ見出せてないようである。確かに巷には「論理的思考」に関する本があふれているが残念ながら、その殆どが論理的思考のフォーマットとプロセスを示しただけのマニュアル本に留まっているのも現状である。
そこで本書は、これらの問題点を意識しながら、本当の意味で「論理的思考」を習得する為には、土台となる思考力を鍛えることが唯一の方法論であるとの確信のもと、“考える”ということをまずきちんと理解した上で、“論理”とは何か、“論理的である”とはどういうことかを学べば「論理的思考」を正しく習得できるというアプローチをとっている。そしてそのアプローチに則って、「思考」の原論、方法論としての「論理」、「分析」のテクニックという三部構成によって、体系的かつ平易で実践的な類書ない「論理的思考」のテキストとしてまとめられている。
本書の目次
Ⅰ章 思考
I-1 思考とは
I-2「分ける」ための三要件
I-3 思考成果
I-4 因果関係
I-5 思考の属人性
第Ⅱ章 論理
II-1 論理とは
II-2 論理展開
II-3 論理展開の方法論
II-4 正しさの根拠
第Ⅲ章 分析
III-1 分析とは
III-2 分析作業
III-3 合理的分析の手法
III-4 論理と心理 |
 >>前のページに戻る >>前のページに戻る |
|
 |
 |
|
■ リーダーシップ構造論
―「リーダーシップ発現のしくみと
開発施策の体系」
波頭亮(著)
産業能率大学出版部
価格:2,310円(税込)
→Amazon.co.jp
近年、戦略的経営を実現するための重要なテーマとして、「リーダーシップ」に対する注目が一層高まっている。今日多くのリーダーシップ研究がなされてきたが、組織運営の方法論としてリーダーシップ全体を体系的かつ構造的に解明した研究は未だ登場し得ていない。そこで本書は、従来のリーダーシップ研究と経営コンサルティングの経験の両面からアプローチした結果、リーダーシップ発現の構造的解明とリーダーシップの開発及び活用の実践的施策について取りまとめたものである。具体的には、①そもそもリーダーシップとは何か②リーダーシップを発現させるファクターは何か③どのようなプロセスでリーダーシップは発現するのか④リーダーシップを意図的に開発するためにはどのような施策が必要かといった、四つの課題に明快な解答を提示している。
本書の目次
第Ⅰ章 リーダーシップの概論
I-1 組織運営の方法論
I-2 マネジメントとリーダーシップ
I-3 リーダーシップ理論の歴史的変遷
I-4 従来のリーダーシップ論の総括と問題点
第Ⅱ章 リーダーシップの構造
II-1 リーダーシップ構造論
II-2 リーダーシップコア
II-3 チームケミストリー
II-4 タスク特性
II-5 組織特性
第Ⅲ章 リーダーシップの開発
第1部 リーダーの育成
第2部 しくみの整備 |
 >>前のページに戻る >>前のページに戻る |
|
 |
| |
|
■ 経営戦略概論
―戦略理論の潮流と体系
波頭亮(著)
産業能率大学出版部
価格:2,592円(税込)
→Amazon.co.jp
経営戦略とは何か、そして有効な経営戦略はどのようにすれば策定することができるのか。この問題に関する理論や学説は多数存在し、それぞれが実証の裏付けを持った研究成果として提唱されている。こうした理論は多様性と各理論の相反性を持っているために、経営戦略の全体像を捉え切ることが難しい。
本書は、この経営戦略論の全体像を明確に描き出すために、有力な戦略理論を一つ一つ紹介・解説した上で、各理論がどのような関係にあるのか検討・整理・体系化したものである。経営戦略論に対する「タテからのスコープ」と「ヨコからのスコープ」によって経営戦略論全体のパースペクティブ(全体の見通し図)を明らかにしている。経営戦略の概論であると同時に経営戦略論の意義と方法論を示した原論でもある。

本書の目次
第Ⅰ部 経営戦略の変遷と戦略理論の発展
第1章 経営学の誕生(1900年代~1950年代)
第2章 経営戦略論への発展(1960年代~1970年代)
第3章 競争戦略の時代(1980年代)
第4章 経営資源と組織の時代(1990年代)
第5章 戦略と組織の融合(1990年代後半)
第6章 リーダーシップの時代(2000年代)
第7章 近年の経営戦略論のテーマ
第Ⅱ部 戦略理論のパースペクティブ
第1章 戦略理論の潮流
第2章 戦略理論の体系
第3章 戦略理論と企業経営 |
 >>前のページに戻る >>前のページに戻る |
|
 |
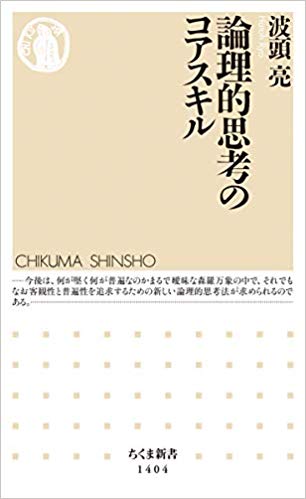 |
|
■ 論理的思考のコアスキル
波頭亮(著)
ちくま新書
価格:929円(税込)
→Amazon.co.jp
論理的思考力を確実に強化するには、論理とは何か、思考とはどのような頭脳行為かを原理的に理解した上で、核となるスキルをトレーニングしていくことが最も有効である。
本書では必須となる3つのコアスキル「適切な言語化」「分ける・繋げる」「定量的な判断」について、習得のためのプログラムを具体的に、体系的に示してある。
“今後は、何が堅く何が普遍なのかまるで曖昧な森羅万象の中で、それでもなお客観性と普遍性を追求するための新しい論理的思考法が求められるのである。”
本書の目次
まえがき
第Ⅰ章 論理的思考とは
第1節 思考とは何か
第2節 論理とは何か
第3節 論理展開の方法
第Ⅱ章 論理的思考のコアスキル
第1節 「適切な言語化」スキル
第2節 「分ける」スキル・「繋げる」スキル
第3節 「定量的な判断」スキル
第4節 アセットとしての知識と経験
第Ⅲ章 コアスキル習得の具体的方法
第1節 what to do:何を練習するのか
第2節 how to do:どう練習するのか
第3節 練習の総時間量:どれくらいやればよいのか
第Ⅳ章 クリティカル・シンキング
第1節 ネイチャーとして間違える脳
第2節 クリティカル・シンキング:それは本当に正しいのか
あとがき |
 >>前のページに戻る >>前のページに戻る |
|
 |
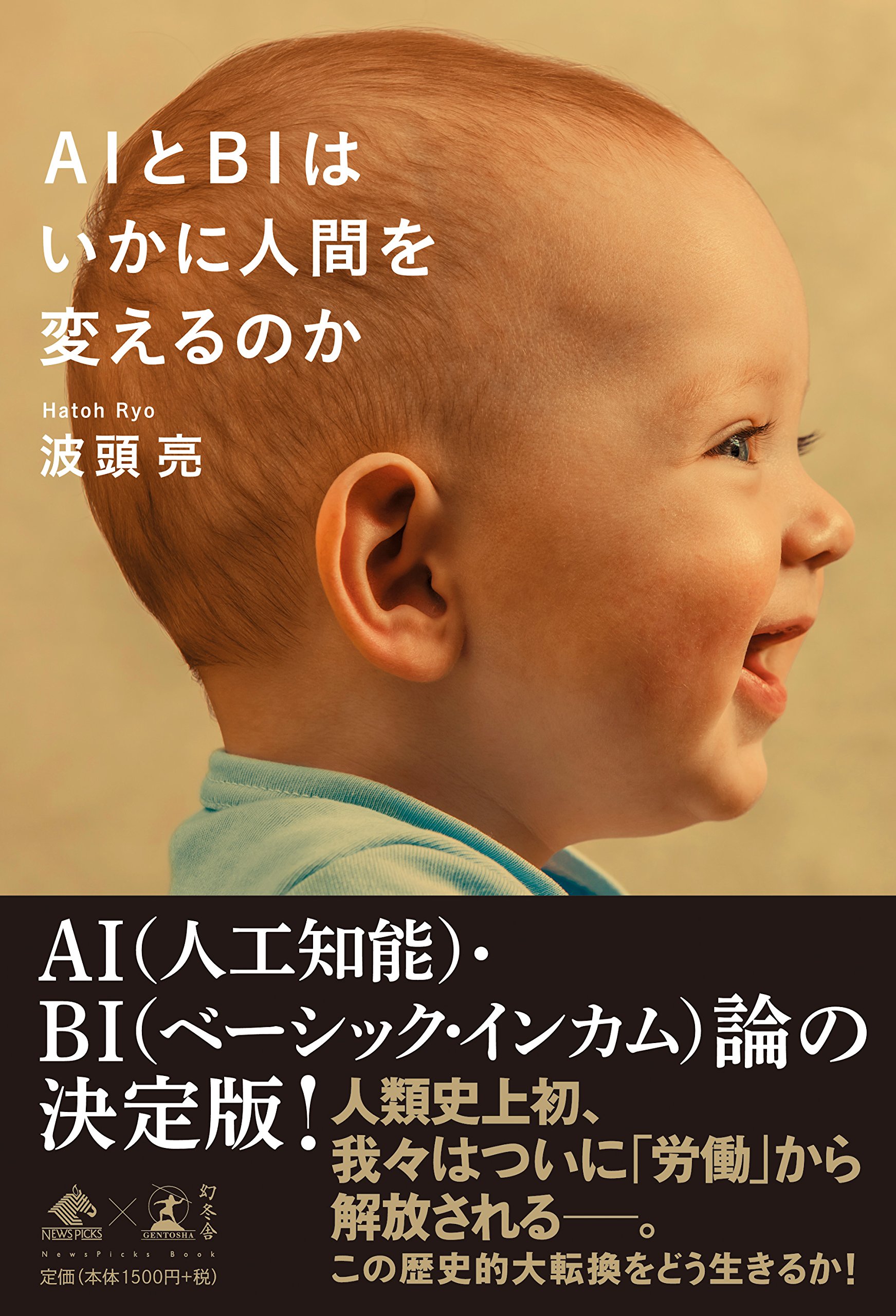 |
|
■ AIとBIはいかに人間を変えるのか
波頭亮(著)
幻冬舎
価格:1620円(税込)
→Amazon.co.jp
歴史を紐解いてみると、産業革命を代表格とする“歴史的大転換”のフェーズがいくつか存在する。そして次の大きな転換点をもたらす革新的技術として注目されているのが、AI(人工知能)である。一方BI(ベーシック・インカム)は、既存の社会保障制度の限界と格差・貧困の深刻化に直面した先進各国が導入を検討している、新しい富の再分配制度である。
このAIとBIが揃った時に社会にもたらされる変化とインパクトは、世の中をユートピアにもディストピアにも変え得るほどに大きい。AIとBIが揃った“新しいステージ”で、豊かな社会と良き人生を実現するために求められることは何なのか。誰もが不安に思い、また誰もが期待をかける本テーマについて、歴史的背景や様々な実情を踏まえてメッセージを述べた、未来への手引書。
本書の目次
まえがき
第Ⅰ章 AI…人工知能とは
第1節 AIとは…AIの発展の歴史
第2節 AIと人間
第Ⅱ章 ベーシック・インカム(BI)の仕組みと効力
第1節 BIの仕組みとメリット
第2節 BIの実現可能性
第3節 民主主義・資本主義とBI
第Ⅲ章 AI+BIの社会で人間はどう生きるのか
第1節 AIとBIが導く“新しいステージ”
第2節 AI+BIの社会で人間はどう生きるのか
あとがき |
 >>前のページに戻る >>前のページに戻る |
|
 |
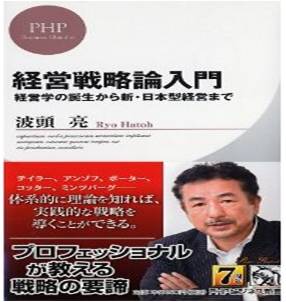 |
|
■ 経営戦略論入門
波頭亮(著)
PHPビジネス新書
価格:860円(税別)
→Amazon.co.jp
「グローバル化」「イノベーション」という最大の経営課題をまえに、日本企業がとるべき「経営戦略」とは、どのようなものか。
本書では、戦略系コンサルティングの第一人者が経営戦略を体系的に解説。前半では、ポーター、コッタ―など経営戦略の原論を取り上げ、後半では、前半をふまえて、「グローバル化」「イノベーション」で成功するために、日本企業が目指すべき新しい経営戦略を考察する。経営戦略の理論と実践が体得できる一冊。
本書の目次
第Ⅰ部 経営戦略論の系譜と分類
Ⅰ-1 マネジメントの誕生と戦略論への進化
1 経営学の基礎が誕生した時代<1930年代まで>
2 経営戦略論の誕生<1960年代>
3 戦略の時代<1980年代>
4 組織とリソースの時代<1990年代>
5 リーダーシップの時代<2000年代>
6 最近の戦略論のトレンド:ゲーム理論と文化研究
Ⅰ-2 戦略論の体系:経営戦略の四つのパターン
1 方法論の軸による分類:「プランニング学派」と
「エマージェンス(創発)学派」
2 戦略タイプによる分類:「ポジショニング学派」
「リソース・ベースド・ビュー学派」
3 戦略の有効性
第Ⅱ部 現代の経営テーマ
Ⅱ-1 現代の企業が直面している問題とは何か
Ⅱ-2 イノベーション
1 イノベーションの難しさ
2 イノベーションを生む経営
Ⅱ-3 グローバル化
1 グローバル化への対応
2 グローバル化のトライ&エラー
Ⅱ-4 新・日本型経営
1 日本的経営とは何だったか
2 新・日本型経営の型を考える |
 >>前のページに戻る >>前のページに戻る |
|
 |
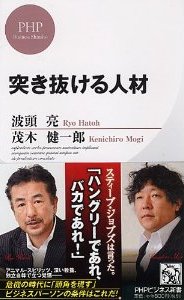 |
|
■ 突き抜ける人材
波頭亮・茂木健一郎(共著)
PHPビジネス新書
価格:800円(税別)
→Amazon.co.jp
感情に突き動かされるアニマル・スピリッツ、“深い教養を身につけ、戦略を打ち立てる知性”、“独立自尊で「志」を貫き、突破する行動力”。
スティーブ・ジョブズ、マーク・ザッカーバーグ、ラリー・ペイジら、時代を切り開く「突き抜ける人材」の凄さとは何か。
彼らのモノの考え方、行動力を徹底分析。さらに、グローバルな観点から、ビジネスの最先端がどう動いているかを紹介。危機の時代に「頭角を現す」ビジネスパーソンの凄さを、豊富なエピソードで語り尽くす。
さらに、「突き抜ける人材」になるための、ビジネス力向上につながるヒントが盛りだくさん。著者の茂木健一郎氏による「茂木塾」構想も発表されている、若手ビジネスマンの心に火を点ける書。
本書の目次
第1章 世界から置き去りにされる日本
第2章 突き抜ける人材、組織はここが違う!
第3章 ガラスの天井を打ち破れ!
第4章 私塾のパワーで日本人を変える
|
 >>前のページに戻る >>前のページに戻る |
|
 |
 |
|
■ プロフェッショナル コンサルティング
波頭亮・冨山和彦(共著)
東洋経済新報社
価格:1,575円(税込)
→Amazon.co.jp
企業のトップマネジメントの仕事が今後ますます高度化・複雑化する中で、
若手コンサルタントや次代を担うビジネスリーダーは今、何を身に付け、
いかに行動するべきか。
戦略系コンサルタントの第1人者・波頭亮氏と、企業再生の実践派コンサル
タント・冨山和彦氏が、コンサルティングの心髄を解き明かす! カネボウ
再生の決め手となったたった1行のソリューション、NTTドコモと
東京デジタルホンのケーススタディ、などこの2人だから話せる経営の
リアルが語り尽くされた対談。
本書の目次
序章 エグゼキューション ケーパビリティの時代
―― 21世紀のビジネス環境を俯瞰する
第1章 日本企業が変革できない本当の理由
―― 経営のリアリティと経営者のリアル
第2章 トップマネジメント・コンサルティングとは何か?
―― コンサルティングの本質とあるべき姿
第3章 プロフェッショナルコンサルタントへの道
―― 若きコンサルタントの働き方
第4章 本物の論理的思考力を身につける
―― ロジカルシンキング&ロジカルコミュニケーション
第5章 東京デジタルホン vs NTTドコモ
―― コンサルティングのケーススタディ
第6章 世界で勝つための日本の戦略
―― グローバル時代の経営とコンサルティング
第7章 「ファクト」「論理」「情理」がすべて
―― コンサルタントの武器と陥りがちな罠
第8章 経営の諸問題はたった1つの施策で解決できる
―― 日本企業がやるべきこと、コンサルタントができること |
 >>前のページに戻る >>前のページに戻る |
|
 |
 |
|
■ 成熟日本への進路
─「成長論」から「分配論」へ
波頭亮(著)
ちくま新書
価格:819円(税込)
→Amazon.co.jp
日本はこれからどの方向に進んでいくのか。政治は迷走し、国民は困惑している。既に成熟フェーズに入った日本は必然的に国家ヴィジョンを差し替えなければならない。そして、経済政策や政治の仕組みを再構築しなければ、社会は一層暗く沈滞していくだけである。国民が「自分は幸せだ」と思える社会の姿と、そうした社会を目指す政策、およびその政策を実行するための戦略と新しい社会のしくみを明快に示す。
本書の目次
Ⅰ章 二一世紀日本の国家ヴィジョン
一 国家ヴィジョンの不在
二 日本が成熟フェーズに入ったことの意味
三 新しい国家ヴィジョン:誰もが医・食・住を保障される国づくり
Ⅱ 経済政策の転換
一 成長戦略は要らない
二 成長論から分配論へ
三 産業構造をシフトする二つのテーマ
四 この国のかたち:社会保障と市場メカニズムの両立
Ⅲ しくみの改革
一 行政主導政治のしくみ
二 官僚機構を構築している四つのファクター
三 官僚機構の改革戦略
四 国民が変わらなければならないこと |
 >>前のページに戻る >>前のページに戻る |
|
 |
 |
|
■ 知識人の裏切り
─どこまで続く、平成日本の漂流
波頭亮(著)
ちくま文庫
価格:924円(税込)
→Amazon.co.jp
高度経済成長至上主義をまっしぐらに突き進んできた日本は、昭和の終わり、狂乱バブルの破綻とともに針路を見失い、平成に入っても長い低迷を続けている。専門主義の狭さと合理主義の浅さでは、人の営為である経済現象をそもそも据えることはできない。なぜ多くの知識人は世論をミスリードしたまま、その誤りを認め修正しないのか。―今日を予言するかのような1992年の対談に、2009年の再検証を加えて刊行。包括的な視野から戦後日本と近代主義そのまのを問い直す、オリジナル文庫。
本書の目次
まえがき 波頭亮
対談1992年
Ⅰ
・欲望という名のメディア
・映像が持つ理性の落とし穴
・八〇パーセントの人のための真理
・オッパイが作りだす視聴率
・テレビ出演のジレンマ
・退屈の中の弱い心に侵入する疫病
・若者が言葉を喪失した八〇年代
・恋愛が成立しないのは男だけの責任ではない
・変革は女性の情緒的行動から始まる
・日本に必ず飢餓が訪れるいくつかの理由
Ⅱ
・「レイバー」「ワーク」「アクション」
・コンピュータ産業革命は勤労に「表現」の部分を残した
・経済一元論では人は幸福を得られない
・変化それ自体の欲望
・言葉を否定してゴキブリ化した日本商人
・市場経済の均質性と島の法則
・奇妙な同質民族
・父殺しの通過儀礼
・死と他者への対峙が言葉を深める
・麻薬以上の快楽
・笑いの甘味は度を越すと毒になる
Ⅲ
・ゼネラリストを評価しない日本
・「一般家」という日本語がなぜないのか
・大衆が選びとる社会的真理
・生き延びることが至上目的の生活者主義
・リビングの否定より始めよ
・価値には序列がある
・思惟から全ては始まる
・言葉こそ経験である―抽象力のすすめ
対談2009年
Ⅰ
・経済学の破綻と、ピュエリル(文化的小児病)の流行
・「公徳」と「私徳」
・「すべて形式化、数量化できる」と考えたことの間違い
・普遍は状況の中でしか語れない
・テクニカル・ナレッジとプラクティカル・ナレッジ
・一つ一つの言葉は歴史を引きずってある
・手段的な意識の異常な発達
・「市」は公正、「競」は平等を意味する
・貨幣は権威に裏打ちされたもの
・インフレで国は潰れるが、デフレで潰れた国はない
・市場経済の大暴走と大敗走は繰り返される
・デモクラシーは軽信すると最悪なシステムになりかねない
・なぜ大衆論は消えたのか
・アメリカの「善意」
・クリスチャニティと「あいまいな日本の私」
・垂直運動と悪人正機説
・男女関係をしっかりやる
・戦争という真剣な比喩
・リアリティーとはバーチャリティーの繰り返しである
・行動する人間は恐ろしい
・日本社会の内部崩壊
・理性と感覚は不可分に繋がっている
・マルクスに足りなかった「経営者」の視点
Ⅱ
・インターネット社会と国家の成熟
・インターネット、二つの論点
情報の民主化/デジタル・デバイド
・凡庸な情報
・コピー&ペーストの知見
・包括的な知見はインターネットでは得られない
・知価社会を崩壊させるリスク
・人間は知価だけでは満足できない
・情報が専門化すると総合知は幼稚になる
・情報を民主化することで、民衆の主体性が損なわれる
・文明の春夏秋冬
・ヨーロッパの賢さ
・拡がり過ぎた版図は崩壊する
・神を殺した我々は、神を生かすこともできるのではないか
・「息つくひまなき刻苦勉励の一生が、ここに完結しました」
あとがき 西部邁 |
 >>前のページに戻る >>前のページに戻る |
|
 |
 |
|
■ プロフェッショナル原論
―「一流であるための掟と日常」
波頭亮(著)
筑摩書房
価格:714円(税込)
→Amazon.co.jp
近年ますます人気化しその活躍が求められている「プロフェッショナルキャリア」。そもそも、自由に華麗に仕事を遂行し、しかも社会からの敬意を得ることができる「プロフェッショナル」という職業が魅力的であることは間違いない。更に、ビジネスの複雑化・高度化を受けて「プロフェッショナル」の仕事の要請は高まるばかりであり、今後一層「プロフェッショナル」の人気が高まっていくのは当然の風潮であるといえよう。
しかしその一方で、実は華やかで目立つ「プロフェッショナル」のイメージとは裏腹に、「プロフェッショナル」本来の社会的役割や厳しい活動の実態については、一般にはあまり知られていない。また、最近では耐震構造偽装やライブドア粉飾決算事件を始め、本来は倫理観の高いはずのプロフェッショナル達による不祥事も頻発し、若いプロフェッショナル達からはSOSの声まで聞こえはじめている。これは明らかに「プロフェッショナル」の世界に何らかの歪みが生じていると考えるべきである。
そこで今、「プロフェッショナル」の本来あるべき姿と仕事のしくみについて真摯にとらえ直してみることは不可欠である。本書では、これまでほとんど紹介されていなかったプロフェッショナルの世界独特の掟からプロフェッショナル達の生活スタイルまで具体的に開示して、プロフェッショナルの世界の実態とあるべき姿を示し、プロフェッショナルという職業の本質を明らかにした。いわばプロフェッショナルがプロフェッショナルとして一流であるための「プロフェッショナリズム原論」である。
本書の目次
第Ⅰ章 プロフェッショナルとは
(1)プロフェッショナルとは
(2)プロとプロフェッショナル
第Ⅱ章 プロフェッショナルの掟
(1)クライアントインタレストファースト
(2)アウトプットオリエンティド
(3)クオリティコンシャス
(4)ヴァリューベース
(5)センスオブオーナーシップ
第Ⅲ章 プロフェッショナルのルールと組織
(1)固有のルール
(2)ギルドとファーム
第Ⅳ章 プロフェッショナルの日常
(1)仕事ぶり
(2)行動特性
(3)人となり
第Ⅴ章 プロフェッショナル達へ
(1)誘惑と不調和
(2)プロフェッショナル達へ |
 >>前のページに戻る >>前のページに戻る |
|
 |
 |
|
■ 若者のリアル
―亡国の世代かネオ=ルネサンスの旗手か
波頭亮(著)
日本実業出版社
価格:1,470円(税込)
→Amazon.co.jp
なぜ勤勉さを嫌悪するのか。仲間うちで激賞し合うのはなぜか。根拠なき自信とプライドはどこから生まれるのか―。 現代の若者に感じる違和感は、単なる世代間ギャップに因るものではない。今後の日本を担う若者の劣化は著しく、憂慮に堪えない事態となってしまっている。社会学的・経済学的アプローチから現代の若者の生き方を分析していくと、最大の問題は彼らの「相場観のズレ、即ち払う対価と得る対価のギャップ」にある。その背景には、社会余剰にパラサイトする若者を許し、甘やかす大人・社会の存在もある。確かに現代の若者は社会的・歴史背景的な必然性をもって生み出されてしまったのではあるものの、このまま若者を容認し続ける限り、創造される価値と消費される価値の不均等、即ち過去の蓄積と未来の可能性を現在の不均等が食いつぶしていくという意味で、近いうちに日本社会は崩壊するだろう。それを回避するには、安逸をむさぼる現代の若者の価値観のズレを矯正させ、社会化していく以外に道は無い。本書は、安逸な若者擁護論に流れず、マクロの視点からポストモダニズムの現状を鋭く抉りながら、日本再生のシナリオを念頭に独自の若者論を展開している。
本書の目次
第Ⅰ章 若者考現学―若者のリアル
1 若者たちのある断章
2 ラクが一番、イマが大切
3 規範の拒否、意味性の否定
4 欲望と計算
第Ⅱ章 若者の系譜―若者の必然と時代変遷
1 六つの世代
2 喪失の系譜
第Ⅲ章 若者のリアルと社会の現実
1 対峙しない若者たち
2 彼らは何を失ったのか
3 相場観のズレ
4「若者流」の検証
5 亡国の必然
第Ⅳ章 再英構想―遊びと自由の時代へ
1 相場観のアジャスト
2 ポストモダニズムの旗手へ |
 >>前のページに戻る >>前のページに戻る |
|
 |
 |
|
■ 就活の法則
―「適職探しと会社選びの10ヶ条」
波頭亮(著)
講談社
価格:1,365円(税込)
→Amazon.co.jp
今日、超売り手市場と言われる一方で、相変わらず入社3年で3割以上の学生が会社を辞めてしまう。この事実は、現在の就職活動のあり方が明らかに非合理であり、経済学的には“市場の失敗”状態になってしまっていることを示している。この状態が今後も長く続くことは個々の学生達を幸せにしないばかりか、企業を弱体化させ、ひいては国家的な損失になってしまうと大変危惧している。
そこで本書は、現在就活市場と就活学生が抱える双方の問題を洗い出し、その上で就活の主体者たる学生に「どうすれば適職を得ることができるか、即ち就活で成功することができるのか」を示すことを目的としている。一人一人の学生が適職を見つけ、その適職が実現する会社を探し出し、首尾よくその会社に入社する為の現実的・具体的な手立てを分かりやすく10か条にまとめたものである。
本書の目次
就活の法則① 「タテ軸指向」から脱却する
就活の法則② 「相対エリート」のポジションを狙う
就活の法則③ 現在の企業人気ランキングは逆に読む
就活の法則④ 「ランキングよりも業種」「業種よりも職種」で選ぶ
就活の法則⑤ HPもOBも本当のことは語らない
就活の法則⑥ 受けるのは5社で十分
就活の法則⑦ 「当たり前のこと」は言わない
就活の法則⑧ 人の評価は、10人中8人は同じである
就活の法則⑨ 「入社後の就活」はハードワーキングである
就活の法則⑩ 入社後5年間は転職しない
おわりに: 就活学生へ、もう一つのメッセージ |
 >>前のページに戻る >>前のページに戻る |